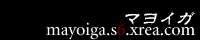橘かおる『大公は彼を奪う』
これは久々にキタワァというか、来た、読んだ、勝った…何にだ?って感じだった。
単純に面白い物語とは違う、またそう来るか~という意外性をつかれる物語とも違う。やっぱりこういうのがあたしのツボなんだろうか、と思ったのだが、どこがツボなのか判然としない。しかし判然としないながらも、高尾理一『夜に濡れる蝶』を髣髴とさせる物語ではあったので、やっぱりこの二作の共通点がツボなのかなあ、とも思う。攻めは徹底的に有能な美丈夫で且つエキセントリック、受けは脆い(実は結構めそめそしたりもするんだよね)ながらも凛々しく強靭、という。
つまり、「ちょっとくらいの問題児ならば、仕方なく全部受け止めてやる」って感じ…アレ?「ちょっとくらいの汚れ物ならば」のもじりのつもりだったんだけど、な、なんか随分全然変わっちゃった…(笑。でもこれなんですよ、多分。ちょっとどころじゃない問題児攻めを「ちょっとくらいの」と言ってしまう度量の広さと、でも「仕方なく」というある種のツンデレ性、それでも「全部」と言ってしまえる雄雄しさ、「~てやる」という主体性、そういう受けが好きです。みたい。
だから絶対、受けはきちんと一人で立てる人間でなければならないし、攻めは問題児でなければならないのです(あ、勿論これらは好きCPのうちの一つであって、他にも好きな設定はいろいろあるんだけれどね。
ということで、北方のシレジアという国の皇帝の従兄弟たる大公=外務大臣×在シレジア日本大使。
まあシレジア=ロシアなわけですが、日本とか、ロシア以外の国はぜんぶ実際の国名で、リャオトン半島の返還問題とかもダイレクトに書かれているので、日清戦争後日露戦争前の三国干渉頃が舞台だと明示されてるも同然。
ロマノフ王家もロストフと言い換えられているんだけれど、やっぱりロマノフはロマンだよなと思った。あたしにとってロマノフロマンはブルボンロマンともハプスブルグロマンともちがうものである。ロマノフファンタジーと言ったほうがいいかもしれない。たとえば狂気ひとつとってもハプスブルグにおけるそれ(ルドルフ二世とかね)よりずっと陰鬱な印象(この印象には本橋馨子の影響があると思うが。
しかし、この世界では日露戦争は回避されそうなのも、何だかツボです(何のツボなんだ?
で、そんな政治的な駆け引きと、大使にメロメロな大公とそれをつっぱねる大使の恋愛の駆け引きが主軸なわけです。全般的に面白かった。
前述の萌えポイントをおさえた駆け引きはすごく好み。お茶を飲んで倒れる際の受けの反応とか、すごく好き。あと最後のオチとかもすごくあたし好み。
これの前作とのからみで、皇帝のあたりの描写やなんかはかなりはしょられているみたいなので、前作も読まなければだ。
亜樹良のりかずの絵は受けが男らしいのでよい。
しかしあれです、高尾理一の前例にもあるように、この作が好みだったからといって、この作家自体があたし好みなのかどうかはまだわからない…うーん、とりあえず他のも読んで見ます。
---
プラチナ文庫がプランタン出版発行の皮をかぶったフランス書院であることに気付いた。